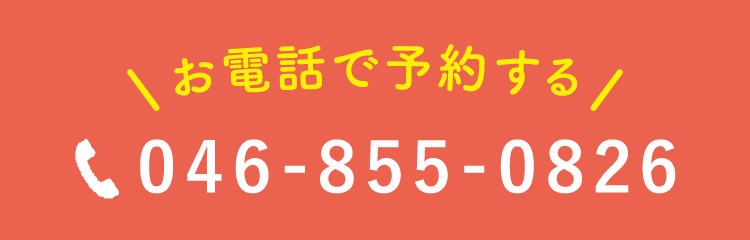マタニティデンタルについて
乳歯はいつごろから作られるのでしょうか?
乳歯は胎生5~9週頃にはすでにお腹の中で作られはじめています。さらに言うと、胎生16週頃には大人の歯である6歳臼歯も作られはじめます。それだけ歯は早い段階で準備されているのです。
妊婦さんが適切な口腔ケアをすることは、早産のリスクを減らすだけでなく、赤ちゃんの歯の健康にも繋がります。ママになろうと決めたら、日常的に口腔ケアを心がけましょう!
妊娠してから歯ブラシの時出血がするようになりました・・・
妊娠中は女性ホルモンの分泌量が増え、その影響で歯周病の原因菌の活動が活発になります。歯肉炎を起こしやすくなるため、腫れや出血などの症状を感じる人もいるでしょう。
症状が気になる人は、歯肉を傷つけないよう優しくマッサージしながら汚れを落としましょう。
また、つわりなどによる口内環境の乱れから、虫歯も悪化しやすくなってしまいます。体調が良い時にぜひ、歯科検診を受けられることをおすすめします。
出産すると歯が弱くなるって聞くけど?
いったん歯に蓄積されたカルシウムが再び体内に摂り込まれることはないため、出産したからといって歯が弱くなるとは限りません。
しかし妊娠中はつわりで食生活が乱れがちになります。また産後も育児で忙しく、自分の口腔ケアが十分にできなくなることもあり、妊娠・出産期に虫歯や歯周病になる人は多い傾向にあるため、こう言われているのかもしれません。
しっかりバランスの良い食事を摂り、正しい口腔ケアをおこなえば、産後も歯を健康に維持することができます。
ベビーデンタルについて
どんなことをするんですか?
0〜3歳のお子さんを対象に行っている健診です。
ここではお子さんが歯医者嫌いにならないよう、おもちゃや本がたくさんあるスペースでお口の中の健診や成長を見させていただいたり、お母さんと一緒に仕上げ磨きの練習をしたり授乳や離乳食についてお話しさせていただいています。
虫歯などで大きな問題がなければ4歳になるまではベビーデンタルで定期健診を行っています。
兄弟をつれていっても大丈夫ですか?
もちろん大丈夫です。
遊ぶスペースもございますし、別の部屋で保育士のお預かりも可能です。
保育の場合はご予約が必要となりますので事前にお申し付けください。(無料)
虫歯予防について
歯磨きをしているのにむし歯になってしまいます
「ちゃんと歯磨きをして治療も終わったのに、どうしてまた虫歯になるの?」
こう感じている方は多いのではないでしょうか。
それは、歯磨きをどれだけ頑張っても、虫歯の本当の原因を解消できていないからです。
その原因は「砂糖」にあります。
砂糖は酸性で歯を溶かしやすく、さらに虫歯菌のエサとなって菌の増殖を促進します。
特にジュースやスポーツドリンクに多く含まれる「ブドウ糖果糖液糖」は注意が必要です。
これらを一日中チビチビ飲んでいたら、虫歯リスクが急増してしまいます。
また、「おやつ=お菓子」ではなく、一度の食事で多くの栄養を取れない子どもたちの4回目の食事として考えることが重要です。
甘いものは歯並びや栄養バランスに影響を与えるので、毎日食べるのではなく、特別な日に楽しんだり、時間を決めて食べるようにしましょう。
さらに、唾液検査で虫歯菌の量を確認し、お子さんに合った予防策を取ることが重要です。
砂糖と上手に付き合いながら、健康な歯を守っていきましょう!
フッ素は使用したほうがいいですか?
どんな食品も適量を大幅にオーバーし、摂取すれば体にとって(塩など)害になることがあります。
歯磨きはいつから始めたらいいですか?
赤ちゃんの乳歯は生後7〜8ヶ月頃に生えはじめます。乳歯が生えてきたら、歯磨きの習慣づけのタイミングです。まずは赤ちゃんが嫌がらないように、無理なく「ガーゼ磨き」からスタートしてみましょう。
また、赤ちゃんのお口や顔まわりは非常に敏感ですので、突然お口を触られるとビックリしてしまうことがあります。歯磨きに慣れるためには、乳歯が生える前からたくさんスキンシップをとり、お口のまわりやお口の中を優しく触れてマッサージしておくことで、歯磨きをスムーズにはじめることができます。
歯磨きを嫌がります。どうしたらいいですか?
いろいろな方法があります。お子さんによってもどれが合うのか違うものです。
よくいわれるのは、「歌を歌いながら楽しく」や「遊びながら」などありますが、1番大切なのは『お子さんにもわかるように歯磨きの必要性を教えてあげること』です。
毎日頭や体を洗うのと同じで、お口の中も清潔にすることが大事です。「お口にたまった歯垢は○んちよりもバイ菌が多いので、きれいにしないとご飯といっしょにバイキン飲み込んじゃうよ〜」などお話ししてあげるのもいいと思います。
また、親御さんが歯磨きしている姿をお子さんにも見せてあげてください。両親がやらないことを自分だけがやるのもお子さんは納得できないものです。仕上げ磨きであれば、お子さんにお父さんお母さんのお口をまず磨かせてあげて交代するのも効果がありますよ。
歯磨き粉は何歳から使うとよいですか?
歯磨き粉はしっかりぶくぶくぺっができるようになってから使いましょう。フッ素のスプレーやジェルは低濃度のものであれば1歳半から使用することもできますが、高濃度のものは5歳以上から使用しましょう。
虫歯が見つかったら削らないといけないと、思っていませんか??
大きくなり痛みを伴うような場合は、今以上悪くならないように痛みがおさまるようにしっかり治療しましょう。
削って治したところは再び虫歯になりやすいので、治療後はしっかりと虫歯になってしまった原因をも治すことが大切です。
そして、歯磨きやフロスをして汚れを落とせば虫歯菌が減り、これもまた予防につながります。
食事指導(食育)について
お菓子やジュースはいつからあげても良いですか?
生涯食べずに済むのであれば食べないのがベストです。 特に3歳までは全く必要ありませんし、むしろこの時期に砂糖を覚えてしまうとやめるのが大変です。
お菓子やジュースなどの砂糖をどれだけ先のばしにできるかで、将来のむし歯も歯並びも決まります。
牛乳もむし歯になりますか?
むし歯になります。牛乳には乳糖と脂肪が多く含まれています。乳糖はじかんを決めずにだらだらと飲んでいればむし歯になります。
また脂肪は満腹感が続き、むら食いや少食、好き嫌いの原因にもなります。
好き嫌いが多いです
お腹は空いていますか?
好きなだけジュースやお菓子を食べていてはお腹が空かず3食の食事は食べられません。
空腹は何よりの調味料!!
おやつ、ジュースの取り方を見直しましょう。
特に野菜嫌いは甘いもの中毒で味覚が壊されてしまっているかもしれません。
お水が飲めない子もジュースの飲みすぎの可能性があります。
お菓子やジュースばかり食べます
ご家族の大人の方がジュースやお菓子ばかり食べていませんか?
常に買い置きがあったり、大人が食べれば子どもも生活習慣が似てしまうのは当然のことです。
では、なぜジュースやお菓子ばかり食べてはいけないかを、お子さんは知っていますか?
当院では、4歳以上のお子さんに1対1でおやつの話しやむし歯の話しをしています。
当院の管理栄養士にお任せください。
離乳食は必ず6ヶ月で始めるものですか?
必ずしも月齢で決めていくものではありません。お子さんの成長に合わせて歯の本数で決めていきましょう。生えている本数で食べ物の形状や硬さを変えてあげることで自然と噛むことやのみこむことへの力がついていきます。
甘いもの(砂糖)は何歳からあげても大丈夫ですか?
基本的に甘いおやつは体に必要なものではありません。少なくとも3歳まではあげないようにしましょう。砂糖依存はこの時期に与えないことで予防できます。
おやつは必要ですか?
おやつは、本来、3度の食事で栄養を十分に摂れないお子さんにとって、4回目の食事として重要です。
そのため、栄養価の高いものを選ぶことが大切です。
しかし、「甘いお菓子」や「ジュース」に含まれる砂糖やブドウ果糖液糖にはほとんど栄養がなく、体に負担をかけるだけです。
よく「甘い物は頭に良い」「疲れたときに甘いものを欲しがる」と言われますが、実際には脳が欲しいのは酸素です。
甘い物を食べることで幸せな気分になることはありますが、体には確実に疲労が蓄積されます。
砂糖やブドウ糖果糖液糖は中毒性があり、体を蝕む原因となります。
WHO(世界保健機構)や欧米の心臓病学会は、砂糖の摂取量を減らすよう強く訴えており、砂糖やジュースに税金をかけるなどの対策が取られています。
これは、砂糖が健康に与える影響が非常に大きいことを示しています。
お子さんの健康を守るため、食事やおやつの選び方を見直していきましょう。
どんなおやつがいいですか?
おやつは「4度目の食事」なので、おにぎりやサンドイッチ、お芋や果物など自然なものがベストかと思います。
お菓子であればおせんべいなどお砂糖や添加物の少ないものを選んであげましょう。体が小さいお子さんにとって砂糖や添加物による体への影響は大人よりも大きいものです。お子さんの健康のために良いおやつを選択しましょう。
食事の時にお水などの飲み物を飲むのが当たり前になっていませんか?
お店に行っても当たり前に出てくるお水はあくまでサービス。
食事をしながら必ずしも飲まなくてもよいのです。
はる歯科クリニックについて
何歳からみてもらえますか?
0歳で歯が生える前から可能です。
早期に知っていただくことでできる虫歯予防や良い歯並びへの発育の方法をお伝えしています。そのため、少しでも早くに受診していただきたいと思っています。
その他
歯ぐきが腫れた
夜寝る前に急に歯ぐきが腫れて痛みや熱が出ることがありますが、これにはさまざまな原因があります。
虫歯が進行して神経が死んで化膿して膿が溜まる場合や、清掃が不十分で腫れること、または歯が生える過程で感染することがあります。
歯以外の原因で腫れることもあり、例えば頬にある唾液腺が詰まったり感染したりすると腫れることがあります。
また、ウイルス感染によっておたふく風邪になることもあります。
どの場合も、早めに小児歯科や小児科を受診することが大切です。
虫歯があったり、虫歯の治療歴がある場合は、歯が原因の可能性が高いです。
歯や歯ぐきに溜まった膿を取り除くことで、痛みが軽減することが多いため、早期の受診が重要です。
腫れた際に氷やアイスノン、冷却シートなどで冷やす方もいますが、冷やしすぎると逆に腫れや痛みが強くなることがあります。
冷やす場合は、タオルを濡らして軽く当てる程度にしましょう。
また、痛み止めを使用する場合は、体に合ったものを使うのが良いですが、膿を取り除かないと痛みが引かないことが多いので、早めに受診することをお勧めします。
さらに、甘いもの(砂糖やブドウ糖果糖液糖)は腫れを悪化させることがあるので、控えるようにしましょう。
特にスポーツドリンクは避け、水を多めに摂るように心がけましょう。
いつも鼻が詰まっている
一年を通して鼻が詰まったり、鼻水がよく出たりしていませんか?
その際、お薬で症状を抑えることが多いかと思いますが、鼻づまりの根本的な原因に目を向けることも大切です。
じつは、鼻づまりと歯の健康には深い関係があります。
鼻が詰まると、鼻呼吸ができなくなり、その結果、口で呼吸をすることになります。
口で呼吸をすると、以下のような影響があります。
・口が乾燥し、虫歯ができやすくなる
・口臭が強くなる
・乾燥した前歯が白くまだらになる
・歯に付いた汚れが乾燥して落ちにくくなる
・口で呼吸することで顎の骨が正しく成長せず、歯並びが悪くなる
さらに、体にも以下のような悪影響が出てしまいます。
・扁桃腺が腫れやすく、風邪やアレルギーが起きやすくなる
・姿勢が悪くなり、猫背になることが多くなる
・顔が長くのびてしまう
・食事中に口を開けて「くちゃくちゃ」食べることが多くなる
・味の濃い食べ物を好み、野菜を嫌がる
・水を飲みにくく、飲まないことが多い
・いつもぼーっとしている
・あくびが多くなる
これらは、お子さんの体にとって不利益な影響を与えることになります。
お薬はあくまで対処療法で、根本的な解決にはなりません。
鼻づまりが続く原因の一つは、口が開いてしまうことです。
しかし、口を閉じることを意識しても、簡単には改善できません。
これらの体の問題を早期に解決するためには、成長期のうちに正しい口の閉じ方を身につけるためのトレーニングを受けておきましょう。
転んだら永久歯が抜けちゃった
転んだりぶつかったりして永久歯が抜けてしまった場合、まずはお口の中に出血があれば清潔なタオルやハンカチ、またはガーゼで5分ほど圧迫し、出血を止めましょう。
抜けた歯は水道水で洗わず、そのまま冷えた牛乳に入れて、急いで歯医者さんに向かってください。
時間が経つと元に戻せる可能性が低くなりますが、30分以内であれば元に戻せる可能性は十分にあります。
重要なのは水道水で洗わず、牛乳に入れることです。
洗ってしまうと塩素が歯の周りの組織にダメージを与えるため、必ずそのまま牛乳に入れてください。
また、もし歯が完全に抜けていない場合は、グラグラした状態でそのまま歯医者さんに急いで行きましょう。
ご飯食べるの遅いし、くちゃくちゃ音がする
もっと早く食べなさい!とか、くちゃくちゃ音立てないで食べなさい!とかお子さんに怒ったりしてませんか?
お子さんはそう言われると頑張って早く食べようとしてくれたり、音を立てないようにと気をつけてくれます。
しかし、どんなに頑張っても自分だけでは直せないことがあります。
お子さんにこのような症状はありませんか?
・鼻詰まり
・イーと噛んだ時に下の前歯が上の前で隠れる(もしくは前歯が噛み合っていない)
・お水やお茶などがないとご飯を食べれなくなっている
・いつもお口が開いている
・唇が一年中カサついたりヒビ割れている
もし、これらに当てはまるものがあれば、それは歯並びの悪さが原因かもしれません。
つまりお子さんの体の機能的に、そう食べざるおえない状況になっているのです。
なのでいくら注意してもお子さん自身でそれを治すことができません。
食事はお子さんの成長にとってとても大切です。
早めに小児歯科で相談することをお勧めします。
成長期のお子さんであれば、改善の可能性があります。
唇の裏にできものが…
特に痛みはないけれど、なかなか治らないできものがある場合、それは「粘液嚢胞」と呼ばれるものかもしれません。
唇を噛んでしまうことにより、唇の裏にある唾液腺が潰れ、そこに唾液が溜まることで膨らんでしまいます。
このできものは、放っておいても自然に治ることもありますが、治るまでに数ヶ月かかることがあります。
また、膨らんでいることで噛みやすく、噛んでしまうことで再度膨らむことが繰り返されることもあります。
そのため、気になる場合は取り除くことも選択肢の一つです。
口内炎との違いは、痛みがないことです。
子どもなのに口が臭いんです
お子さんの口臭が気になる方は多いですが、歯磨きをしても臭いが取れない場合、いくつかの原因が考えられます。
① 口呼吸
1番多い原因がこの口呼吸です。
お口が開いていると口の中が乾燥し、臭いが発生します。
また、扁桃腺やアデノイドの腫れからくる炎症も臭いの原因になることがあります。
これが進行すると、鼻づまりや中耳炎を引き起こし、臭いが強くなることもあります。
② 甘いものの食べ過ぎ
甘いものは口内の虫歯菌を増やし、胃を乾燥させることがあります。
甘い物を多く摂取しているお子さんには、特有の口臭が見られることがあります。
③成長期に起こるホルモンバランスの影響
第一次・第二次成長期にホルモンバランスが変化することがあり、それが原因で口臭が起こることもあります。
このようにさまざまな原因で口臭が起きますが、特に口呼吸と甘い物が関係しています。
これらは口臭だけでなく、虫歯や歯並びの問題を引き起こし、健康にも悪影響を及ぼすことがあります。
思い当たることがあれば、早めに改善することが大切です。
小帯について検診で指摘されました
上唇小帯が永久歯が生える時期まで残っていると、前歯に隙間ができることがあります。
そのため、永久歯が生えた後も上唇小帯が残っている場合、歯医者さんから切除を勧められることがあります。